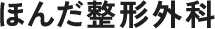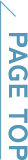この記事でわかること
- 足首が痛くなる原因とその仕組み(筋肉・靭帯・骨・神経など)
- 足首の痛みを部位別(前側・内側・外側・後ろ)に見た特徴
- 足首の痛みに隠れている可能性のある病気(関節リウマチ・痛風・血流障害など)
- 足首の痛みを和らげる治しかた・セルフケア・ストレッチ方法
- 整形外科を受診すべき症状の目安
足首が痛い
 「朝起きて立ち上がった瞬間に、ズキッと足首が痛む」
「朝起きて立ち上がった瞬間に、ズキッと足首が痛む」
「特に捻った覚えもないのに、なんとなく歩くと違和感がある」
そんな“原因がよくわからない足首の痛み”を訴える方は、実はとても多いです。
見た目には腫れがなくても、靭帯の微細な損傷や腱の炎症、足首のバランスの崩れが隠れていることがあります。足首は、地面から伝わる衝撃を吸収しながら体を支える関節。
日々の立ち方・歩き方・靴の形が少しずつ影響し、知らないうちに関節や腱に負担をかけてしまうことがあります。
足首が痛いのはなぜ?原因とメカニズム
 足首の痛みは外傷だけでなく、筋肉・腱・靭帯・骨・神経など、複数の組織が複雑に関係して起こることが多いのです。
足首の痛みは外傷だけでなく、筋肉・腱・靭帯・骨・神経など、複数の組織が複雑に関係して起こることが多いのです。
筋肉や腱の使いすぎによる痛み
最も多いのは、筋肉や腱の疲労・炎症による痛みです。長時間の立ち仕事、運動、合わない靴などが続くと、足首を支える筋肉(後脛骨筋・長腓骨筋など)に微細な炎症が起こります。
特に、足首の内側に痛みが出る場合は、「後脛骨筋腱機能不全症(こうけいこつきんけんきのうふぜんしょう)」が疑われます。これは、アーチ(土踏まず)を支える腱に炎症が生じ、歩くたびにズキッと痛む・内くるぶしの下が腫れるといった症状を伴うものです。
また、ランニングやジャンプ動作を繰り返すことでアキレス腱炎や腱鞘炎が起こり、
足首の後方や外側が痛むこともあります。
靭帯や関節の不安定性
「捻っていないのに痛い」場合でも、過去の捻挫が原因で、靭帯が伸びてしまっているケースがあります。靭帯はのびてしまっていると、関節の安定性が失われ、ちょっとした動きでも炎症を繰り返します。
この状態を足関節不安定症と呼び、放置すると変形性足関節症になることもあります。
特に、階段を降りる時・坂道を歩く時に「なんとなくグラつく」「踏ん張ると痛い」と感じたら注意が必要です。
骨や軟骨のトラブル
腫れていないのに足首が痛い原因として、疲労骨折や軟骨の損傷が隠れていることもあります。
特にマラソン・バスケットボールなどで繰り返し負荷がかかると、踵骨(しょうこつ)や距骨(きょこつ)に小さなヒビが入る「疲労骨折」が発生します。
初期は痛みが軽く、レントゲンでも写らないことがあるため、「筋肉痛だと思っていたら骨折だった」というケースも珍しくありません。痛みが長引く場合はエコー・MRIなどの精密検査が必要です。
神経・血流の問題
神経の圧迫による痛みも見逃せません。足首の内側を通る神経が圧迫されると、「しびれ」「ピリピリ感」「焼けるような痛み」が出ることがあります。これは足根管症候群と呼ばれ、足の裏まで違和感が広がるのが特徴です。
また、冷え性や血流の悪化によっても、筋肉が固まり、足首の奥に重だるさを感じることがあります。
体の使い方や姿勢の癖
実は、足首の痛みは全身のバランスとも関係しています。猫背・骨盤の歪み・偏平足などがあると、体重のかかり方が偏り、片方の足首ばかりに負担がかかります。
💡特に、立っているときに足の内側に重心が偏る人は要注意。この歩き方は、後脛骨筋腱や内側の靭帯を過度に引っ張り、「捻っていないのに内くるぶしが痛い」状態を招きやすくなります。
足首が痛い(前側・内側・外側など)
 足首が痛いとき、「どこが痛むか」で原因はまったく違います。
足首が痛いとき、「どこが痛むか」で原因はまったく違います。
前がズキッとする、内側がピリッとする、外側が重だるい。同じ“足首の痛み”でも、その裏には別々のトラブルが隠れていることが多いのです。ここでは、痛む場所ごとの特徴と原因をわかりやすく整理しました。
足首の痛み「部位別の特徴」
足首の痛みは、「どの場所が痛むか」で原因が大きく異なります。
同じ“足首が痛い”でも、前・内側・外側・後ろなど、痛む部位によって関係する筋肉や靭帯、関節のトラブルが変わるのです。ここでは、部位ごとに考えられる代表的な原因と特徴を整理して紹介します。
足首の前側が痛いとき
「つま先を上げたときに足首の前が痛い」「階段を下りるとズキッとする」
そんな痛みは、足首の前面の腱や関節に負担がかかっているサインです。
主な原因としては、
前脛骨筋腱炎(ぜんけいこつきんけんえん)
つま先を上げる筋肉(前脛骨筋)が酷使されて炎症を起こす。ランニングやハイヒールなどで繰り返し負担がかかると発症しやすい。
前方インピンジメント症候群
足首を反らすたびに骨や軟骨がぶつかり合い、炎症が起こる。スポーツ選手に多く、長引くと軟骨損傷の原因にも。
足関節の捻挫後遺症
過去の捻挫で靭帯が緩み、前方の関節包に炎症が残っていることもあります。
💡腫れていなくても、内部で滑膜炎(かつまくえん)や関節包の炎症が進んでいる場合があります。
つま先を上げたり、深くしゃがむ動作で痛む人は要注意です。
足首の内側が痛いとき
足首の内側のくるぶし周辺に痛みがある場合は、腱や靭帯のトラブルが多く見られます。
代表的なのが、
後脛骨筋腱機能不全症(こうけいこつきんけんきのうふぜんしょう)
土踏まずを支える腱に炎症が起こる病気。内側のくるぶし下あたりがズキッと痛む/押すとピリッとする/アーチがつぶれる、という症状が特徴です。
三角靭帯損傷
捻っていないのに痛むケースもあり。内側の靭帯が伸びて不安定になると、立つだけで痛むこともあります。
変形性足関節症(初期)
加齢や過去の捻挫により、軟骨がすり減って痛む。初期は内側の違和感から始まります。
💡 歩き方が「内側重心」の人、扁平足気味の人は内側痛が出やすい傾向があります。
足首の外側が痛いとき
足首の外側は、最も捻挫が起こりやすい部位。ただし、「捻っていないのに外側が痛い」場合も少なくありません。考えられる主な原因は、
腓骨筋腱炎(ひこつきんけんえん)
外くるぶしの後ろを通る腱がこすれて炎症を起こす。ランニングや長時間の立ち仕事で悪化することが多いです。
足関節外側靭帯損傷(慢性化)
以前の軽い捻挫が治りきらず、靭帯が緩んで関節が不安定な状態。
平地でもグラつく、夕方に重だるいと感じる人は要注意。
腓骨筋腱脱臼
腱がくるぶしの後ろから前にずれてしまう病態。動かすたびに“パチッ”と音が鳴るのが特徴。
💡外側痛を放置すると、靭帯のゆるみが進行して再発を繰り返す「慢性捻挫」の原因にもなります。
足首の後ろ(アキレス腱周囲)が痛いとき
後ろ側の痛みは、アキレス腱やその周囲の炎症によるものが中心です。
アキレス腱炎/アキレス腱周囲炎
ふくらはぎの筋肉のかかと付け根に炎症が起きる。ジャンプ・ランニング・坂道歩行で悪化。
ハグルンド変形(踵の骨突出)
靴のかかと部分が当たって炎症を起こす。若い女性やスポーツ愛好家に多い。
アキレス腱付着部症
踵の骨との付け根に炎症が起こり、押すと強く痛む。
💡靴の形・サイズが合わない場合や、固いヒールカウンターが当たると悪化します。
足首が腫れているとき/腫れていないのに痛いとき
腫れている場合は、捻挫・骨折・滑膜炎・痛風・感染などの可能性があります。
一方で、腫れていないのに痛い場合は、慢性的な炎症・腱の微小損傷・疲労骨折の初期など、
“内部で静かに進むトラブル”が隠れていることがあります。
腫れていないのに痛い例
- 後脛骨筋腱炎
- 足根管症候群
- 初期の変形性足関節症
- 微小な疲労骨折
見た目で判断せず、痛みが続く場合は整形外科でのMRI検査をおすすめします。
足首の痛みに隠れている病気
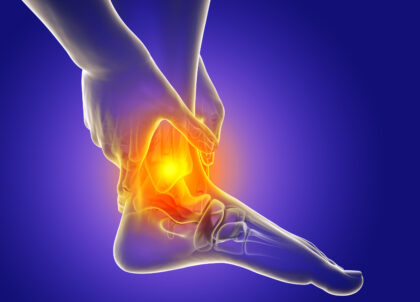 「捻っていないのに痛い」「腫れていないのに重だるい」そんな足首の痛みが、体の中の病気から来ているサインであることもあります。足首の関節は、体の中でも血流や代謝、免疫の影響を強く受けやすい部位です。ここでは、整形外科だけでなく内科・代謝・免疫の領域と関係する病気を紹介します。
「捻っていないのに痛い」「腫れていないのに重だるい」そんな足首の痛みが、体の中の病気から来ているサインであることもあります。足首の関節は、体の中でも血流や代謝、免疫の影響を強く受けやすい部位です。ここでは、整形外科だけでなく内科・代謝・免疫の領域と関係する病気を紹介します。
関節リウマチ(免疫の異常で起こる炎症)
関節リウマチは、体の免疫システムが誤って自分自身の関節を攻撃してしまう病気です。
手指の関節のイメージが強いですが、足首にも初期症状が出ることがあります。
特徴としては
- 朝起きたときに足首がこわばる
- 動き出すと少し楽になる
- 晩になると再び痛みや腫れが増す
こうした「朝のこわばり」は、リウマチの典型的サイン。放置すると関節の変形につながるため、早期の血液検査が重要です。
痛風・偽痛風(尿酸やピロリン酸カルシウムの結晶による炎症)
「夜中に突然、足首がズキッと痛む」「触れるだけで激痛」という場合は、痛風発作が疑われます。
多くは足の親指の付け根(母趾MTP関節)に起こりますが、足首に現れるケースもあります。
尿酸が関節内にたまり、結晶化して炎症を起こすのが原因。
一方で「偽痛風」はピロリン酸カルシウムの結晶が関節内に沈着して炎症を起こします。
どちらも血液検査やレントゲンで診断できますが、放置すると再発や腎臓への影響も出ます。
糖尿病性神経障害
糖尿病を長く患っている方では、神経の障害による痛みが足首や足の甲に現れることがあります。
特徴としては
- 足首や足の甲がピリピリ・ジンジンする
- 夜に痛みが強まる
- 触れるだけでピリピリ痛い、または感覚が鈍くなる
腫れがないのに痛いケースでは、神経性の痛みを疑う必要があります。
血糖コントロールを整えることが最優先の治療になります。
末梢動脈疾患(血流の障害)
「歩くと足首やふくらはぎが痛くなるけど、休むと治る」そのような症状は、末梢動脈疾患(PAD)の可能性があります。足に血液を送る動脈が動脈硬化などで細くなり、酸素不足で筋肉が痛む病気です。
進行すると、足の冷え・しびれ・皮膚の色の変化なども見られます。この病気は心臓病・脳梗塞のリスクと深く関係するため、整形外科よりも循環器内科での精密検査が必要です。
骨の壊死・血流障害(距骨壊死など)
まれに、足首や手首などの小さな骨の内部が壊死する病気があり、血流障害によって骨がつぶれてしまうのが特徴です。
距骨壊死では、
- 捻った覚えがないのに足首がズキズキ痛い
- 動かすと関節の奥で痛む
- MRIでしか見つからない
といった特徴があります。長引く足首痛がある場合は、骨壊死も念頭に置く必要があります。
足首の痛みの治しかた・セルフケア
足首の痛みは、安静にしていれば治ることもありますが、原因によっては「休むだけでは治らない」ことも少なくありません。ここでは、自宅でできるセルフケアと、整形外科で行われる治療の両面から、回復を早めるポイントを紹介します。
まずは“動かさない勇気”も大切に
痛みが強い初期は、無理に動かさず安静を保つことが最優先です。歩行時に痛みが出る場合は、足首に体重をかけずに過ごしましょう。特に「ズキッ」「ジンジン」と痛む場合は炎症のサイン。
湿布や冷却(アイシング)で熱を抑えることが効果的です。
🔹冷却の目安
1回15〜20分、1日2〜3回を目安に。タオルを挟んで凍傷を防ぎましょう。
痛みが落ち着いたら“動かすリハビリ”へ
炎症が収まってきたら、足首を支える筋肉(特にふくらはぎとすねの筋肉)をゆるめ、再び動かす段階へ。
軽いストレッチ例
足首回し
イスに座って、片足をゆっくり回す。左右10回ずつ。→ 血行を改善し、関節の可動域を保つ。
タオルギャザー
床にタオルを敷き、足の指でたぐり寄せる。→ 足裏と足首の安定性を高める。
かかと上げ運動
立ったまま、両かかとをゆっくり上げ下げ。10回×2セット。→ ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)を鍛え、血流改善に◎。
どの運動も「痛みが出ない範囲で」「ゆっくり」が基本です。
温めて血流を整える
慢性的な痛みや重だるさが残る場合は、冷やすよりも温める方が効果的。
- お風呂にゆっくり浸かる
- 蒸しタオルで足首を包む
- (38〜40℃程度)を10分ほど
冷えがあると血流が滞り、修復が遅れてしまうため、温めて代謝を促すことが回復の鍵になります。
靴選び・歩き方を見直す
足首の痛みを繰り返す人に多いのが、“合っていない靴”と“癖のある歩き方”。
- ヒールや先の細い靴は、足首の安定性を損なう
- クッション性がなく、すり減った靴底は衝撃を吸収できない
- 内側や外側に重心が偏る歩き方は、足首に負担をかける
自分に合った靴を選び、インソールでアーチを支えることで、
再発の予防にもつながります。
整形外科で行う治療
自宅ケアで改善が見られない場合は、整形外科での治療が有効です。
- 薬物治療:痛み止め・消炎剤・湿布などで炎症を抑える
- リハビリ療法:ストレッチ・電気治療・筋トレで再発を防ぐ
- 装具療法:足首サポーターやインソールで安定化
足首の痛みは、冷やす・休むだけでは根本改善しません。原因に合わせて「休める→動かす→整える→支える」ステップで少しずつ回復を目指しましょう。痛みが長引く場合や、再発を繰り返す場合は、整形外科での精密検査・リハビリ指導をおすすめします。