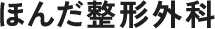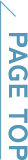骨折・打撲・捻挫の違いとは?
 「転んだあとから痛いけど、腫れてないし、動かせるから大丈夫」そんな経験、ありませんか?
「転んだあとから痛いけど、腫れてないし、動かせるから大丈夫」そんな経験、ありませんか?
実は、“骨折・打撲・捻挫”は見た目や初期症状がよく似ていて、見た目が軽くても骨にヒビが入っている(不全骨折)ケースも珍しくありません。これら3つのケガは、いずれも外からの衝撃で起こりますが、損傷する部位と深さが異なります。
| 名称 | 損傷の部位 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 骨折 | 骨そのものが折れる/ヒビが入る | 強い痛み、腫れ、変形、動かすと激痛 |
| 打撲(打ち身) | 皮膚や筋肉・血管などの軟部組織 | 鈍い痛み、腫れ、内出血、押すと痛い |
| 捻挫 | 関節の靭帯・関節包など | 腫れ、関節のグラつき、歩行時痛 |
初期には「ただの打撲かな?」と思っても、実際には骨折や靭帯損傷を伴っていることもあります。
たとえば
- 骨折でも腫れが少ない
- 捻挫と思って放置したら靭帯断裂だった
というケースは、整形外科では非常に多く見られます。早期に正確な診断を受けることで、
回復が早まり、後遺症を防げるのがこれらの外傷の大きな特徴です。
骨折とは?
 骨折とは、外から加わった力によって、骨が部分的または完全に折れてしまう状態を指します。転倒や衝突のような強い衝撃はもちろん、くしゃみや日常動作といった小さな力でも骨折することがあります。
骨折とは、外から加わった力によって、骨が部分的または完全に折れてしまう状態を指します。転倒や衝突のような強い衝撃はもちろん、くしゃみや日常動作といった小さな力でも骨折することがあります。
骨折の主な種類
通常の骨折(外傷骨折)
転倒や打撲など、大きな衝撃で起こる一般的な骨折。骨が完全に折れる「完全骨折」と、ヒビが入る「不全骨折」があります。
注)ヒビといっても骨折です!レントゲンでずれが指摘できないだけでれっきとした骨折です!!
疲労骨折
ランニングやジャンプなどの繰り返し動作による微細な骨の損傷です。
初期は「痛いけど腫れていない」ことが多く、単なる筋肉痛や打撲と誤認されやすい骨折です。特に部活動やマラソンなど、長時間の運動を続ける方に多く見られます。
骨脆弱性骨折
骨粗しょう症で骨密度が低下し、骨がもろくなった状態で起こる骨折です。
「軽くつまずいて手をついた」「尻もちをついた」「重いものを持った」だけで折れることがあり、高齢者に非常に多いタイプです。
大腿骨や背骨(椎体骨折)など、生活に大きな影響を与える骨折も少なくありません。
病的骨折
腫瘍や炎症などによって骨が弱くなり、わずかな力で折れてしまう骨折です。
通常では折れない程度の衝撃で骨折が起こるため、基礎疾患の早期発見にもつながる重要なサインです。
骨折の原因とリスク要因
骨折の原因は、スポーツや転倒、交通事故などの外的要因だけではありません。
骨密度の低下・成長期の未成熟な骨・筋力不足・バランスの悪化など、内的要因も関係します。
- 高齢者:つまずき・尻もち・階段での転倒による手首・股関節の骨折が多い
- 子ども:遊具や転倒などによる前腕・肘の骨折が多い
特に中高年以降は、骨粗しょう症検査(骨密度測定)を定期的に受けることで、骨折予防にもつながります。
骨折のサイン(こんな症状は注意)
- 動かすと鋭い痛みが走る
- 腫れや変形がある
- 力が入らない、しびれを感じる
- あざ・内出血がある
「動かせるから大丈夫」「腫れていないから打撲だと思う」と自己判断して放置すると、不全骨折や靭帯損傷が悪化し、治りが遅くなることがあります。
迷ったときは、整形外科でレントゲン・CT検査・エコー検査などを受けましょう。
骨折の治療法
骨折の場所・ずれの程度・年齢などによって治療方法は異なります。基本的な流れは次の通りです。
- 整復(せいふく):ずれた骨を元の位置に戻す、※ずれが大きいときは手術が必要です!
- 固定:ギプス・副子(添え木)・シーネなどで動かさないようにする
- リハビリ:骨の癒合後、関節の可動域や筋力を回復させる
ずれが大きい場合や関節にかかる骨折では、手術によるプレート固定やピン固定が必要なこともあります。早期に治療を始めることで、骨の再生力を最大限に生かし、機能をしっかり取り戻すことができます。
注)手術は骨折のずれをできるだけもとに戻す治療であり、治癒を促進するものではありません!
打撲とは?
 打撲とは、転倒や衝突などで皮膚・筋肉・血管などの軟部組織が損傷を受け、内部で出血や炎症が起きた状態を指します。「打ち身」とも呼ばれ、外からは軽く見えても、筋肉の奥に血腫(内出血のかたまり)ができている場合があります。頭部や眼部などでは、脳や眼球そのものを傷つける危険性があり、打撲といえども注意が必要です。
打撲とは、転倒や衝突などで皮膚・筋肉・血管などの軟部組織が損傷を受け、内部で出血や炎症が起きた状態を指します。「打ち身」とも呼ばれ、外からは軽く見えても、筋肉の奥に血腫(内出血のかたまり)ができている場合があります。頭部や眼部などでは、脳や眼球そのものを傷つける危険性があり、打撲といえども注意が必要です。
打撲の主な原因
-
- 転倒して地面や壁などに体をぶつけた
- 物に衝突したり、落下物が当たった
- 接触スポーツや事故などで強い衝撃を受けた
- 暴力などで体を打たれた
日常の中でも起こりうるケガで、特に高齢者や子どもでは転倒による打撲が多く見られます。
打撲の症状(部位別の特徴)
打撲は部位によって症状が異なります。軽度な痛みでも、内部損傷や合併症の可能性があるため注意が必要です。
①太もも・腕などの筋肉打撲
- 腫れ、圧痛、内出血
- 曲げ伸ばし時の痛み
- 数日後、皮膚が青紫色に変色(皮下出血の吸収過程)
特に太ももの打撲では「筋挫傷」と呼ばる筋肉の損傷もあり、重度の場合は筋肉内血腫ができ、治癒まで数週間かかることもあります。
② 頭部の打撲
- 頭痛、ふらつき、吐き気、めまい
- 記憶があいまい、意識がもうろうとする
これらの症状は脳震盪(のうしんとう)や頭蓋内出血のサインであることがあります。
「少しぶつけただけ」と思っても、頭を打ったら即受診が原則です。
整形外科ではなく、脳の専門家である脳神経外科を受診しましょう!!
③ 目の打撲(眼部打撲)
- 目の痛み、視力の低下、視界がかすむ
- 出血や涙・液体が漏れる
これらの症状は眼球破裂や網膜損傷の可能性があり、眼科での緊急対応が必要です。
整形外科ではなく、目の専門家である眼下を受診しましょう!!
④ 歯・口の打撲
- 歯ぐきの腫れ、出血、歯のぐらつき強い衝撃で歯の根が折れていることも
歯がぐらついたり欠けた場合は、歯科口腔外科の受診が必要です。
打撲の治療とセルフケア
🔹 初期48時間は「冷やす」
炎症や腫れを抑えるため、氷や保冷剤をタオル越しに10〜15分程度冷却を繰り返します。
冷却しながら包帯などでケガの周りを圧迫し、居城して安静にすることで、内出血や腫れの拡大を防ぎます。(RICE療法)
※ 直接氷を当てると凍傷の恐れがあるため注意。
🔹 その後は「温めて回復促進」
1週間以上経って腫れが落ち着いたら、温熱療法に切り替えて血流を促します。
温めることで老廃物の排出と筋肉の回復が促進されます。医師やリハビリスタッフの指導のもと、電気治療・温熱療法・軽いストレッチなどを行うと回復が早まります。
受診の目安(こんなときは整形外科へ)
- 痛みや腫れが3日以上続く
- 手足のしびれ・麻痺・違和感がある
- 頭や目を強く打った➡脳神経外科や眼科などの専門科の受診を!!
- 腫れがどんどん広がる、熱をもっている
これらの症状がある場合、単なる打撲ではなく、骨折・神経損傷・筋肉断裂の可能性があります。
「数日待てば治る」と自己判断せず、早めの整形外科受診が早期回復のカギです。
捻挫とは?
 捻挫とは、外からの力で関節を支える靭帯・関節包・軟骨などが損傷した状態を指します。多くは足首や手首で起こりますが、膝関節・肩関節などでも発生します。
捻挫とは、外からの力で関節を支える靭帯・関節包・軟骨などが損傷した状態を指します。多くは足首や手首で起こりますが、膝関節・肩関節などでも発生します。
一見すると軽いケガに思えても、靭帯の部分断裂や関節内損傷を伴っている場合もあり注意が必要です。
特に膝の捻挫は、痛みが軽度でも半月板損傷や前十字靭帯損傷が隠れていることがあるため、「少しひねっただけ」と軽視せず、整形外科での診断が大切です。
捻挫の主な原因
- 足首を内側・外側に強くひねる
- スポーツ中のジャンプや着地で足をねじる
- 段差や階段で足を踏み外す
- 交通事故などの強い衝撃
- 転倒時に手をつく、あるいは体重を支えようとする
スポーツや日常動作の中で誰にでも起こりうるケガです。
特に女性や子どもは関節が柔らかく、足首をひねりやすい傾向があります。
捻挫の症状
- 関節の痛み・腫れ
- 内出血による皮膚の変色(青〜紫)
- 熱感・圧痛
- 関節がぐらつく・力が入らない
- 動かすとズキッと痛む
軽度の捻挫では「歩けるけど痛い」ことが多く、見た目の腫れも少ないため見逃されがちです。
しかし、靭帯の部分断裂や関節包損傷がある場合、そのまま放置すると再発や関節の不安定性につながります。
捻挫の治療法とセルフケア
急性期(受傷から48時間以内)は、RICE処置が基本です。
- Rest(安静):痛みのある部分を動かさない
- Icing(冷却):氷や保冷剤を10〜15分ずつ当てて炎症を抑える
- Compression(圧迫):包帯やテーピングで腫れを防ぐ
- Elevation(挙上):患部を心臓より高くして血流を調整する
その後は、医師の判断によりギプスやテーピングで固定し、必要に応じて鎮痛剤やリハビリ療法を行います。重度の靭帯損傷では、内視鏡手術などによる修復が必要になることもあります。
受診の目安
- 腫れや痛みが強い・長引く
- 体重をかけるとズキッとする
- 関節がグラグラする感覚がある
- 何度も同じ箇所を捻る
これらの症状がある場合は、「軽い捻挫」ではなく靭帯損傷や骨折の合併が考えられます。
歩けるからといって放置せず、整形外科で正確な診断を受けましょう。