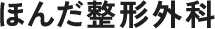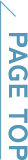この記事でわかること
- 手足のしびれの原因とメカニズム(神経・血流・姿勢など)
- 整形外科で扱う代表的なしびれの病気(ヘルニア・脊柱管狭窄症・手根管症候群など)
- 部位別に見た手足のしびれの特徴と原因
- 放置すると危険なしびれのサインと受診の目安
手や足がジンジン・ビリビリしびれる原因は?
 「手がしびれる」「足の感覚が鈍い」——そんな症状に悩んでいませんか?
「手がしびれる」「足の感覚が鈍い」——そんな症状に悩んでいませんか?
多くの方が「脳の病気では?」と不安に感じますが、実は 整形外科で扱う“神経の圧迫”や“関節・筋肉の障害” が原因で起こることも非常に多いのです。
たとえば、
✅首の神経が圧迫されて腕にしびれが出る「頸椎椎間板ヘルニア」「頚椎症性脊髄症」
✅腰の神経が圧迫されて脚がしびれる「腰椎椎間板ヘルニア」や「脊柱管狭窄症」
といった疾患は、整形外科で頻繁にみられる代表的な病気です。
しびれの多くは、神経が通る道が狭くなる・圧迫されることで感覚が乱れ、
「ジンジン」「ビリビリ」といった異常な感覚として現れます。
しびれは「神経からのSOSサイン」
しびれとは、神経が一時的または慢性的にうまく働けなくなっているサインです。
たとえば正座をしたあとに足が“ジーン”とするのも、神経が一時的に圧迫されて血流が滞っているために起こるもの。このように、神経の働きが乱れると、痛みや感覚異常として体に現れます。
しかし、中には早期治療が必要なタイプのしびれも存在します。
時間が経つほど神経は回復しにくくなるため、「なんとなくしびれる」「原因が思い当たらない」ときほど、早めの受診が大切です。
整形外科で多い“しびれの原因”とは
整形外科領域でみられる「しびれ」は、主に以下のような疾患や状態が関係します。
| 原因カテゴリ | 主な疾患・状態 | 特徴 |
|---|---|---|
| 脊椎や関節の異常 | 頸椎椎間板ヘルニア/腰椎椎間板ヘルニア/脊柱管狭窄症 | 神経が骨や椎間板に圧迫されることで起こる |
| 末梢神経の障害 | 手根管症候群/肘部管症候群/足根管症候群 | 関節付近のトンネル状構造で神経が締め付けられる |
| 内科的要因 | 糖尿病性神経障害/動脈硬化/末梢循環障害 | 神経への血流・栄養が不足し感覚異常が生じる |
こうした「整形外科で扱うしびれ」は、構造的な圧迫や血流の障害によって起こることが多く、
MRIや神経伝導検査などで原因を正確に特定できます。
整形外科で診る手足のしびれの原因
 手足のしびれは、整形外科領域では主に神経の圧迫・血流障害・筋肉の緊張・姿勢のゆがみなどが関係します。しびれの根本には、「神経がうまく働けていない」という共通点があります。以下では代表的な原因を詳しく見ていきましょう。
手足のしびれは、整形外科領域では主に神経の圧迫・血流障害・筋肉の緊張・姿勢のゆがみなどが関係します。しびれの根本には、「神経がうまく働けていない」という共通点があります。以下では代表的な原因を詳しく見ていきましょう。
神経の圧迫によるしびれ(最も多いタイプ)
脊椎や関節の周囲で神経が圧迫されることによって起こるしびれです。
代表的な疾患には次のようなものがあります。
- 頸椎椎間板ヘルニア:首の神経が圧迫され、腕・手のしびれや痛みを引き起こす
- 腰椎椎間板ヘルニア:腰から脚へ伸びる坐骨神経を圧迫
- 脊柱管狭窄症:加齢や姿勢不良により神経の通り道が狭くなる
- 手根管症候群・肘部管症候群・足根管症候群:関節付近の神経が通るトンネル状部分で神経が締めつけられる
| 症状の部位 | 主な疾患名 |
|---|---|
| 手のしびれ | 手根管症候群・肘部管症候群・頸椎ヘルニア |
| 足のしびれ | 足根管症候群・坐骨神経痛・腰椎ヘルニア・脊柱管狭窄症 |
初期には「ビリビリ」「ジンジン」「感覚が鈍い」といった違和感が中心ですが、
進行すると筋力低下や動かしにくさが現れることもあります。
血流障害によるしびれ
手足の血行が悪くなると、神経への酸素・栄養供給が不足し、しびれが生じます。
原因としては、冷え・動脈硬化・糖尿病・末梢循環障害などがあります。
- 冷え・血管疾患によるしびれ → 体を温めると改善する
- 神経障害によるしびれ → 温めても改善しない
温めても症状が変わらない場合は、神経障害の可能性があり、整形外科の診察が必要ですが、内科などでの診察が必要となる場合もあります。
筋肉の緊張によるしびれ
首・肩・腰などの筋肉が過度に緊張すると、その間を通る神経や血管が圧迫されます。
これにより、「コリ+しびれ」という複合的な症状が起こることがあります。
- 長時間のデスクワーク
- スマホ操作によるストレートネック
- ストレスによる筋緊張
など、現代的な生活習慣が背景となることが多く、姿勢改善やストレッチで軽快するケースもあります。
姿勢や体の使い方の問題
猫背・反り腰・片側荷重などの姿勢のゆがみによって、筋肉や神経に負担がかかり、慢性的なしびれが出ることもあります。特に近年は、スマホ首(スマホシンドローム)やデスクワーク姿勢の悪化が原因の患者さんが増えています。
手足のしびれ|部位別でわかる原因と危険サイン
 しびれの感じ方は、どの神経がどこで圧迫されているかによって異なります。「手がしびれる」「足がしびれる」といっても、どの指・どの部位に症状が出るかで、原因となる神経をある程度特定できます。ここでは、整形外科でよく見られる“部位別のしびれ”の原因を詳しく解説します。
しびれの感じ方は、どの神経がどこで圧迫されているかによって異なります。「手がしびれる」「足がしびれる」といっても、どの指・どの部位に症状が出るかで、原因となる神経をある程度特定できます。ここでは、整形外科でよく見られる“部位別のしびれ”の原因を詳しく解説します。
手のしびれ
手のしびれの多くは、手首・肘・首のいずれかで神経が圧迫されることによって起こります。
整形外科でよく診断される代表的な疾患を見ていきましょう。
手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)
手首の内側(手のひら側)にある「手根管」というトンネルの中を通る正中神経が圧迫されて起こります。親指・人差し指・中指・薬指の半分にかけて“ジンジン”“ピリピリ”としびれるのが特徴。
- 夜間や朝方にしびれが強くなる
- 指を振ると楽になる(いわゆる「シェイクサイン」)
- 物をつまむ動作がしにくくなる
原因は、手の使いすぎ・ホルモン変化・ガングリオンなどの圧迫。
放置すると、親指の付け根(母指球筋)がやせて、細かい作業が難しくなることもあります。
肘部管症候群(ちゅうぶかんしょうこうぐん)
肘の内側を通る尺骨神経が圧迫されることで起こる疾患です。
小指と薬指の半分にしびれや感覚鈍麻が出ます。
- 肘を長時間曲げる(スマホ操作・寝姿勢)
- 肘をよくぶつけるクセがある
といった生活動作が原因になります。
進行すると、手の細かい動き(ボタンを留める・箸を使う)が難しくなり、指が変形(かぎ爪変形)することもあります。
頸椎椎間板ヘルニア・頸椎症性神経根症
首の骨(頸椎)の間で神経が圧迫され、肩〜腕〜指先にかけてしびれや放散痛が出るタイプです。
首を後ろに反らすとしびれが強くなることが多く、ストレートネック(スマホ姿勢)に関連するケースも増えています。
足のしびれ
足のしびれは、腰椎や足首まわりの神経圧迫で起こることが多く、
神経が圧迫される部位によって、太もも・ふくらはぎ・足先など、症状の出る範囲が異なります。
腰椎椎間板ヘルニア
腰の椎間板が飛び出して脊髄を圧迫する病気です。
「腰から脚の後ろ側にかけてのしびれや痛みが電気が走るように出る」が典型的で、くしゃみ・前かがみで悪化することが多いです。特に20〜50代の男性や運動習慣のある人に多く見られます。
腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)
加齢や姿勢の変化により、神経の通り道(脊柱管)が狭くなり脊髄を圧迫する病気です。
特徴は「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれる症状。
歩くとしびれ・痛みが出て、少し休むと軽くなるのが特徴です。
高齢者に多く、長時間の歩行が難しくなる傾向があります。
足根管症候群(そっこんかんしょうこうぐん)
足首の内側にある「足根管」で脛骨神経が圧迫される病気。
足の裏全体のしびれ・灼けるような痛みが特徴です。
原因は、
- 扁平足(足のアーチが低い)
- ガングリオンなどの腫瘤
- 長時間の立ち仕事
放置すると、歩行時の違和感や痛みが慢性化することがあります。
一過性のしびれ(短時間で治まるタイプ)
正座やうつ伏せ寝などで一時的に神経や血管が圧迫されると、「ジーンとする」「足がしびれる」といった感覚が出ますこれは神経が一時的に酸欠状態になっているだけで、血流が戻れば自然に治まります。ただし、以下のような場合は注意が必要です。
- しびれが長時間続く
- 繰り返し起こる
- 感覚が戻らない・鈍い
これらは神経障害の初期サインである可能性があります。早めに整形外科で検査を受けましょう。
放置すると危険な手足のしびれ
 「そのうち治るだろう」と思ってしびれを放っておくと、知らないうちに神経がダメージを受け続け、回復しにくい状態に進行することがあります。神経の障害は、時間が経つほど治りにくくなるのが特徴です。「いつのまにか指の力が入らない」「ペンを落とす」「段差でつまずく」など、運動機能に影響が出てきたら、すでに神経が弱っているサインです。
「そのうち治るだろう」と思ってしびれを放っておくと、知らないうちに神経がダメージを受け続け、回復しにくい状態に進行することがあります。神経の障害は、時間が経つほど治りにくくなるのが特徴です。「いつのまにか指の力が入らない」「ペンを落とす」「段差でつまずく」など、運動機能に影響が出てきたら、すでに神経が弱っているサインです。
⚠️ 放置してはいけない“危険なしびれ”のサイン
- しびれが数週間以上続く
- 夜間や安静時にもジンジンする
- 感覚が鈍く、熱さや痛みを感じにくい
- 筋力が低下してボタンが留めにくい、歩きにくい
- 痛みや冷感を伴う
- しびれが左右どちらかに限局している
これらの症状は、神経の圧迫や炎症、血流障害が進行している可能性があります。とくに、糖尿病や動脈硬化などの基礎疾患がある方は、早期受診が重要です。
しびれは「早めの診断」で守れる機能があります
手足のしびれは、単なる疲労や一過性の圧迫で起こることもありますが、
その裏に神経や血流のトラブルが隠れていることも少なくありません。
整形外科では、しびれの原因を“構造的”に分析し、筋肉・骨格・神経のバランスから根本改善を目指します。
「しびれはまだ軽いから」と我慢せず、早い段階で相談することで、回復できる範囲を最大限に広げることができます。気になる症状やお悩みがあれば、ご相談ください。